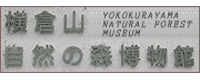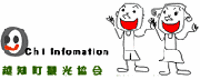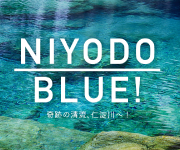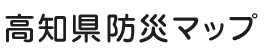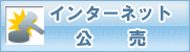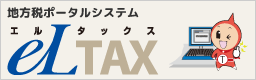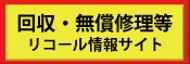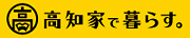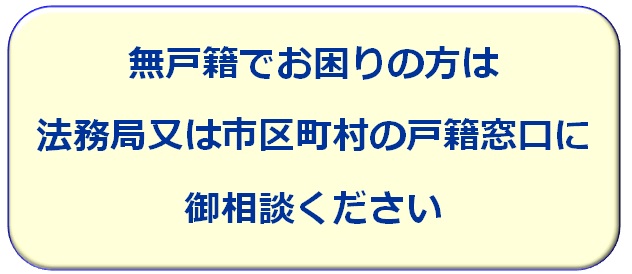令和6年10月の制度改正より、児童手当において監護する第3子以降の支給児童の支給額(月額)が、30,000円に増額することとなりました。第3子認定には認定請求(申請)手続きが必要となる場合があります。
第3子認定に係る変更点と提出資料等について
▼支給児童ごとの児童手当月額
令和6年10月の制度改正以降、児童手当において監護する支給児童等について、支給額(月額)は下記のとおりです。
・3歳未満 : 15,000円
・3歳~18歳 : 10,000円
・第3子以降 : 30,000円
▼第3子(以降)とは
児童手当制度における第3子以降の数え方は、監護する支給児童及び算定対象(児童の兄姉)等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。一般的な続き柄の「長男」「長女」や「三男」「三女」とは異なり、23歳以上の兄姉は含みません。下記リンク資料もご覧ください。
>>第3子以降のカウント方法について<< (こども家庭庁資料)
▼第3子認定の認定請求(申請)手続き
監護する3人(以上)の子に、19歳~22歳の子が含まれる場合、通常の児童手当の手続きに加えて、別途資料の提出が必要です。監護する3人(以上)の子が、すべて支給児童(0歳~18歳)のみであれば、通常の児童手当の手続きだけで第3子認定も完了します。
▼第3子認定請求(申請)の提出資料
・額改定認定請求書(別添記載例C参照)(3月時点で18歳の高校3年生年代児童がいる場合のみ)
・監護相当および生計費の負担についての確認書(別添記載例B参照)
・別居する子(学生)の学生証等の写し(不鮮明でなければコピーでも可)
・別居する子(学生以外)の生活費負担の証明資料(振込みが分かる通帳等の持参)
※提出資料については、ご家庭により異なる場合がありますので、お電話等で事前にご相談ください。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
※※ ご注意ください ※※
(児童手当制度における年齢計算等については、一般的な数え方と異なる場合があるため、必ず下記をご確認ください。)
▼子の年代・学年の範囲
法律上、年齢は誕生日の前日に加算されるため、4月1日生まれの子は前日3月31日に加齢することから、誕生日を基に考えた場合「4月2日~翌年4月1日生まれ」までが1年代(1学年)の範囲となる。
▼子の年齢(年代・学年)の判断
就学の有無は関係なく「次の3月31日時点で年齢到達している年代(学年)かどうか」で判断される。
・支給児童 : 0歳~18歳(次の3月31日時点で19歳となっている子は対象外)
・算定対象 :19歳~22歳(次の3月31日時点で23歳となっている子は対象外)
▼支給児童
児童手当が支給される0歳~18歳までの児童。次の3月31日時点で18歳の子までが該当。なお、児童手当の支給には認定請求(申請)手続きが必要。
▼算定対象
児童手当支給対象外の19歳~22歳の子だが、認定請求(申請)手続きを行うことで、支給児童である弟妹を第3子認定するための算定対象として第1子・第2子に数えることが可能。なお、前述のとおり23歳以上の子は除外される。
▼監護
保護し監督すること。子を養育し生計を維持していることと考えて差し支えない。
児童手当制度においては、以下の条件のいずれかが伴わない場合、監護していると見なされない。
・申立人が子と同居して生計を一にしている。
・申立人が別居する子の生計を維持している。
・申立人が学生である子の学費を負担している。
▼生計の維持
申立人の継続的な援助により、子の日常生活が成り立っており、申立人の援助を欠くと子の生活が維持できない。
申立人が援助を打ち切っても子が生活できる場合、子は監護されているとはいえない。
▼子の状態の変更と「監護相当および生計費の負担についての確認書」等資料の更新・再提出
19歳~22歳までの監護する子について、既に「監護相当および生計費の負担についての確認書」を提出している場合でも、進学・就職・離職・卒業(退学含む)等、子の状態が変更となった場合、速やかに確認書等資料を更新・再提出する必要がある。特に就学中の子は「卒業予定時期」を記載しているため「子は卒業後どのように生活するか」について、原則として卒業前までに再提出すること。
確認書等資料の更新・再提出がない場合は、状態変更日(卒業等)以降の申立てがないものと見なし、第3子認定できず30,000円支給の対象から除外されるため注意が必要。なお、前述のとおり、次の3月31日で23歳以上となっている子は除外される。
▼高校卒業後の算定対象への認定について
18歳の高校3年生で3月に卒業する支給児童等がおり、弟妹を第3子認定するため、4月以降は19歳年代の算定対象に加えたい場合「額改定認定請求書」および「監護相当および生計費の負担についての確認書」等資料の提出が必要。手続きをしないと算定対象へ移行しないため要注意。
【問合せ先】 越知町 住民課 児童手当担当 ℡:0889-26-1115 (9時~17時 土・日・祝日を除く)
※お電話でご相談を承りますが、本人確認ができないため、一部情報をお伝えする事ができかねる場合があります。ご了承ください。
※越知町以外から児童手当を支給されている方は、児童手当の支給元にご確認お願いします。